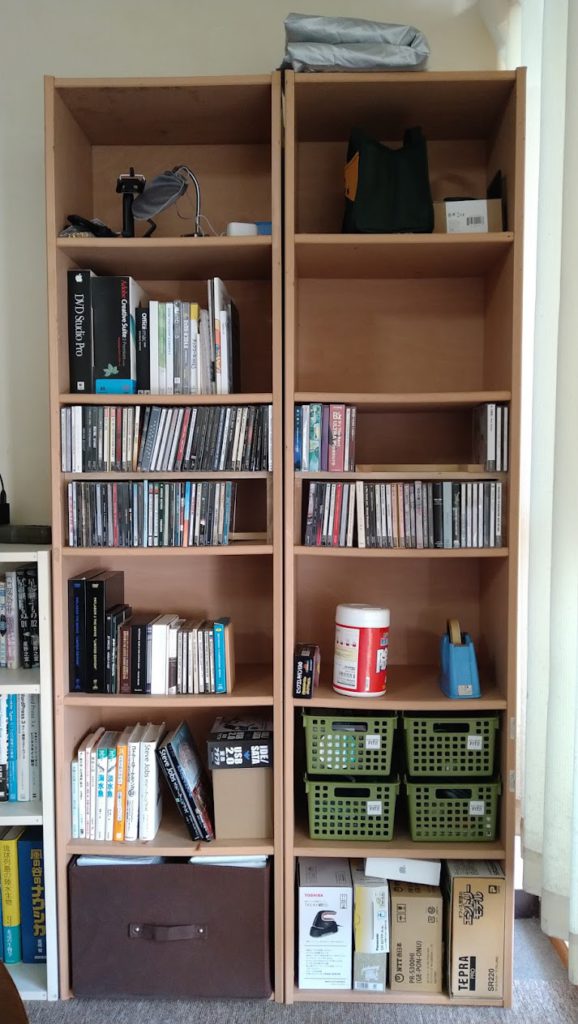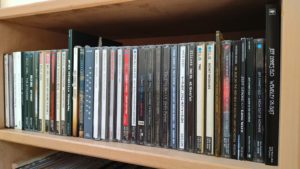4月に USB オーディオ・インターフェースを買い替えて、ふふふ、これからは標準プラグの時代だぜとばかりにヘッドバンド・カバーを付けたヘッドホンを手にしてみれば。思えば Mac 周辺以外に標準プラグを使える機材がなくなっていたー。
その後、面倒くさがり続けること3ヶ月。7月の終わりになって、テレビラックの中で眠っていたフルサイズのヘッドホン・アンプ付き AD-DA コンバーター(走行系に問題のある DAT デッキとも言う)を、読書コーナーに召喚することにしたのです。

CD プレイヤー代わりの DVD レコーダーと DAT デッキを光デジタル接続し、録音モニター状態にしてヘッドホンに音を出してやろうって寸法。ちゃんと使えて、ほっ。それに、ひょこひょこ動くレベルメーターって、やっぱ、イイわぁ。

かくして、読書コーナーには、90年代の半壊した DAT デッキと、00年代の退役 DVD レコーダーと、包帯を巻かれた10年代のヘッドホンと、同じく10年代の車載スピーカーユニットを再利用した手作りスピーカーと、20年に購入した小型の格安アンプが集結しました。
なんか、どれも信頼性に欠ける面々ですが、とりあえず、音はソコソコ良いです。

そして、DAT デッキが消えたテレビラックには、Nintend0 Switch が配置されましたよ、と。めでたしめでたし。…いや、新しく買ったゲーム機を置くために DAT をどけたわけじゃないんだからねっ!