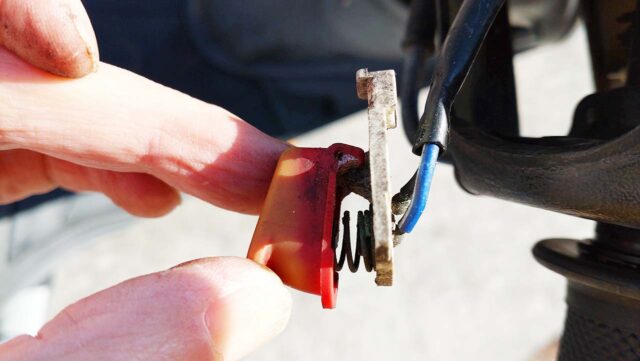2002年頃に購入した PM-4000PX が、とうとう壊れました。

インク不足を訴えていたカートリッジを新しいモノに交換しても、正しく認識してくれず、赤ランプが点きっぱなし。カートリッジを抜き差ししても、電源を入れ直しても、果てまた古いカートリッジに戻してみても、なにも変わらず。ただただ、赤く光るのみ。
ここ15年くらい、日常の印刷にはより安くて速くて静かな別機種を使っていて、PM-4000PX は、年に1度か2度の「ここ一発の高画質」が必要な時にだけ使う感じでしたからね(ちなみに最後に使ったのは、ほんの1ヶ月前)。よく保った、というか、よく保たせてしまったというか、20年以上、お疲れ様でした、です。
にしても。プリンター本体の寿命がどうこうよりも、こんなにも長い間、旧製品用インクカートリッジが売られ続けていたことが、つくづく不思議でありました。ありがたかった、ですけどね。もちろん。