過去にフジの廉価なサービス(150万画素相当)で手持ちのネガフィルムを全てデジタル化していたものの、単価の高いリバーサルと白黒フィルムを放置しつづけ幾歳月。そんなことを思い出してしまったのが運の尽き。フィルムスキャナーの購入を検討することにしました。

で、調べてみたら、今ってやっすいのとたっかいのと両極端で選択肢がほとんどないのですね。そんだったら、やっすいので良いです、私。

選んだのは6千円弱のサンワサプライのフィルムスキャナ。USB給電の本体と、フィルムホルダー(6コマ)とスライドマウントホルダー(3コマ)、それに原稿台のクリーニングシートのセットです。
本体には何のボタンもなく、ホルダーをグサッと刺して同梱ソフトでリアルタイム・プレビューしながら手作業で位置合わせを行い、そしてキャプチャボタンをクリックしてスキャン(というより接写撮影?)する、といった極めてザックリとした商品でした。
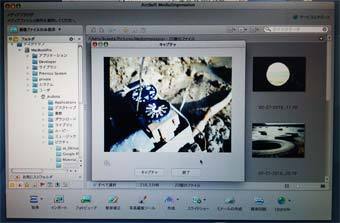
CMOS の解像度は517万画素だそうです。設定で色深度を 24bit か 32bit か選択できますが、色や明るさの調整は一切なし。全て機械任せ。スキャン時間は数秒で、かつ大半はファイルの書き込み時間じゃなかろうかという印象です。
1コマごとに設定で悩む要素もなければ待ち時間もほとんどないオモチャ感覚なので、脇目も振らずにチャッチャカ作業できます。
実のところ、過去に EPSON のフィルムスキャナや透過原稿台つきフラットベッドスキャナとか持っていたんですけど、1コマ1コマに気を使い過ぎて疲れちゃったんですよね(結果、業者に出したと)。そこらへん、ソコソコ画質で高速デジタル化してくれるんなら、それはそれでアリじゃんと割り切れちゃう点で、良い製品(笑)。割り切れない人は、たぶん手を出してはいけない製品。

難点は、ダイナミックレンジの広さ(というか狭さ)。コントラストが強い写真は、上の2点の例の通り白トビ黒ツブレ気味。白黒ネガでは気になりませんでしたが、ポジは残念な傾向にあります。右上のエアーズロックは救えないだろうなぁ…。さりながら、この商品では割り切りがキモなので、割り切っちゃいましょう。左上の写真を Photoshop でトーンカーブ調整したものが下の写真(ホコリ取り等レタッチなし)。

現在のコンベンション・センター周辺
PENTAX Super-A / smc A 28mm F2.8
作業フローとしては、1)スキャンしてTIFF保存 2)撮影年月日と現像番号/フィルムロール名とコマ数を加味したファイル名にリネーム 3)Photoshop で調整&レタッチして PSD保存(原版扱い) 4)JPEG書き出し(プリント扱い) 5)JPEG を iPhoto に登録して Exif(撮影日時)を改訂 と、いった感じになりそうです。…と、書いてて面倒くさくなってきた。白黒とポジ限定で点数が少ないのが救いですね。
そうそう、同梱の画像ソフト(MediaImpression 2)でキャプチャ時に「モノクロ」フィルムで「TIFF」保存を選択すると、白黒256階調のインデックスカラーとして記録されます。このため、Photoshop での作業時にグレースケールにモード変換する必要がありましたよ、と。その点、ご注意を。
※JPEG保存は眼中になかったので試してません。

 これまで K-S2 には、TAMRAC の着脱式ショルダーストラップを付けていました。*istDs を使っていたときに購入して、K10D に付けていたモノを伝承していたのです。なのですが、以前のカメラ達とは違って、K-S2 ではプラスチック製のカメラ本体をストラップのバックルでゴリゴリこすってしまうことがママあります。形状やバリアングル液晶の位置関係などの所為なんだろうけど、かなりヤな感じ。
これまで K-S2 には、TAMRAC の着脱式ショルダーストラップを付けていました。*istDs を使っていたときに購入して、K10D に付けていたモノを伝承していたのです。なのですが、以前のカメラ達とは違って、K-S2 ではプラスチック製のカメラ本体をストラップのバックルでゴリゴリこすってしまうことがママあります。形状やバリアングル液晶の位置関係などの所為なんだろうけど、かなりヤな感じ。 かといって、わざわざ買い替える気にもならなかったので、Super-A につけていたストラップと交換することにしました。学生時代にヨドバシで買ったシロモノ(たぶんペンタ純正品)ですが、意外なくらいキレイな状態を保っておりましたし。
かといって、わざわざ買い替える気にもならなかったので、Super-A につけていたストラップと交換することにしました。学生時代にヨドバシで買ったシロモノ(たぶんペンタ純正品)ですが、意外なくらいキレイな状態を保っておりましたし。 ということで、トレード。
ということで、トレード。 ちなみに、TAMRAC のハンドストラップも持っていて、K10D では状況に応じてストラップを使い分けていました。そういう面では着脱式って素敵なんですけどね…。それが今や K10D と Super-A に取付けられたよ、と。出番あるのか、着脱式。
ちなみに、TAMRAC のハンドストラップも持っていて、K10D では状況に応じてストラップを使い分けていました。そういう面では着脱式って素敵なんですけどね…。それが今や K10D と Super-A に取付けられたよ、と。出番あるのか、着脱式。 私らは、ちょうど色んなモノが「マニュアル操作が当たり前」から「自動操作が当たり前」に移りゆく過程にあった世代です。
私らは、ちょうど色んなモノが「マニュアル操作が当たり前」から「自動操作が当たり前」に移りゆく過程にあった世代です。 もひとつ世代を絡めた私個人の特徴として挙げられるのが、一眼レフカメラ。その履歴は、露出計すらついていなかった祖父の KONICA FP に始まり、その後 PENTAX ME Super→
もひとつ世代を絡めた私個人の特徴として挙げられるのが、一眼レフカメラ。その履歴は、露出計すらついていなかった祖父の KONICA FP に始まり、その後 PENTAX ME Super→