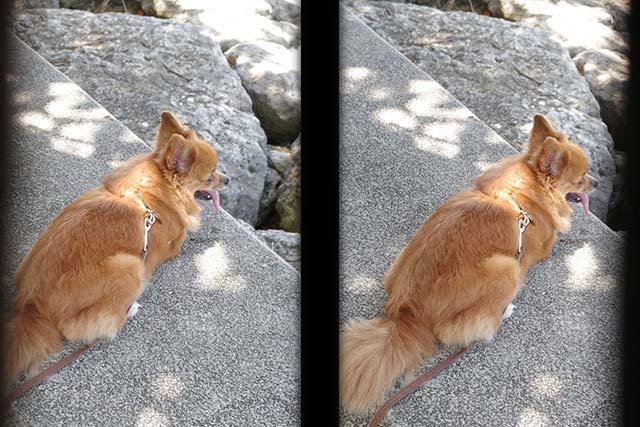ごく、たまーに、望遠レンズが欲しいな、と思うときがあります。気分的には DA★ 200mm。でも、高い。かといって、ミドルクラスの 300mm ズームだと、画質は担保できそうだけど半端に高くて半端にデカくて、しかも暗い。となると、費用対効果含めて割り切り易いのは DA 50-200mm WR の中古品か…。ホッソリとした HD DA 200mm F4 WR なんてシロモノが、ホドホド価格で存在すればいいのに。
ごく、たまーに、望遠レンズが欲しいな、と思うときがあります。気分的には DA★ 200mm。でも、高い。かといって、ミドルクラスの 300mm ズームだと、画質は担保できそうだけど半端に高くて半端にデカくて、しかも暗い。となると、費用対効果含めて割り切り易いのは DA 50-200mm WR の中古品か…。ホッソリとした HD DA 200mm F4 WR なんてシロモノが、ホドホド価格で存在すればいいのに。
なんてことを考えていた、そんな折。キットレンズ DAL 50-200mm WR の別売フード付中古品が、送料込みで約8千円という、大変お求め易い価格で売られていたのを目にしてしまった訳ですよ。ほんとにねぇ。困りますねぇ
 WR の証の赤いOリングと、
WR の証の赤いOリングと、
DAL の証のプラマウント。
単品販売レンズから省かれているのは、フード、クイック・シフト・フォーカス(QSF)、前玉の SP コート、そして距離目盛。目盛を省くんかっ!と割り切りの潔さにミョーに感心したりして。
 3月に荒天用レンズとして中古購入していた DA 18-55mm F3.5-5.6 AL WR との比較。50-200 の方が若干長くて重いけど、収納時の存在感はほぼイコールです。
3月に荒天用レンズとして中古購入していた DA 18-55mm F3.5-5.6 AL WR との比較。50-200 の方が若干長くて重いけど、収納時の存在感はほぼイコールです。
 DA 17-70mm F4(中央)と、おまけで A 35-105mm F3.5(右)も並べてみた最伸長時の比較。いずれも望遠端で、A はマクロ位置です。
DA 17-70mm F4(中央)と、おまけで A 35-105mm F3.5(右)も並べてみた最伸長時の比較。いずれも望遠端で、A はマクロ位置です。
太さは、明らかに 50-200 が細いものの(だってフィルター径が 49mm と 67mm ですもの)、伸ばした時のかさばり方は似たようなものですね。いささかフードがデカイってこともありますが。
 K-S2 につけたところ。18-55mm よりも少し長い分だけ、手が大きめの私にはフォーカスリングに指をかけやすいです。それに 18-55mm に比べればズームリングが重いこともあって、ピント合わせしようとしてズームリングまで動かしてしまう、ということは起こりにくそう。いや、QSF がないなら MF で使えばいいやと考えていたので、結構重要だったり。
K-S2 につけたところ。18-55mm よりも少し長い分だけ、手が大きめの私にはフォーカスリングに指をかけやすいです。それに 18-55mm に比べればズームリングが重いこともあって、ピント合わせしようとしてズームリングまで動かしてしまう、ということは起こりにくそう。いや、QSF がないなら MF で使えばいいやと考えていたので、結構重要だったり。
言うまでもなくフォーカスリングはスカスカ。思いのほか回転角が大きくて戸惑いました(なおさら距離刻みが欲しい…)。滑り止めラバーの指がかりの良さに救われている感じでしょうか。
使ってみての印象はこちら。
※7年後、HD DA 55-300mm F4.5-6.3 ED PLM WR RE を購入しました。