 春先、スピーカーの外回りを布巾でフキフキしていたときに、気まぐれにサランネットを外してみたのです。したら、ウーファー外周部がボロッボロ…、その周辺には白いポツポツが大量に…。
春先、スピーカーの外回りを布巾でフキフキしていたときに、気まぐれにサランネットを外してみたのです。したら、ウーファー外周部がボロッボロ…、その周辺には白いポツポツが大量に…。
どうも、カビに有機物が吸い取られてカピカピに干涸び、朽ちてしまったご様子。経年劣化もあるのだろうけど、特にここ8年半は海チカでしたから、環境要因も大きいのだろうなぁ…。
ユニット構成を入れ替えながらも、90年代半ばから ONKYO INTEC 205 シリーズを使い続けてきた私。朽ちたのは、初期ラインアップで単品販売されていた D-102Aでした。さいきんステレオで音楽を流す頻度が下がっていたし、集合住宅だから音量も控えめにしていたし、そして恐らくはカビによる浸食が徐々に進行していたということもあるのでしょう。ちっとも異変に気づきませんでした!
 ということで、スピーカーを買い替えることに。東京に居たときなら、ヨドバシなり秋葉原なりで店頭試聴してから決めていたでしょうけれど、沖縄の家電量販店にはそんな環境がない。かといって街ナカのオーディオショップ(まだ数件生き残ってる)は、専門化がどんどん進んで高額商品しか扱っていなさそうな気がする。よって、不本意ながら通販することにしました。
ということで、スピーカーを買い替えることに。東京に居たときなら、ヨドバシなり秋葉原なりで店頭試聴してから決めていたでしょうけれど、沖縄の家電量販店にはそんな環境がない。かといって街ナカのオーディオショップ(まだ数件生き残ってる)は、専門化がどんどん進んで高額商品しか扱っていなさそうな気がする。よって、不本意ながら通販することにしました。
そうなるとね。私の場合、もう20何年も耳にしていた ONKYO 製品でリプレイスするのが妥当。選ぶ楽しみが限定される反面、音の好みの面でハズレが少ないでしょうから。そこで選んだのが、ネット上で評判が良く、そして都合良く型落ちして安く売られていた D-112EXT でした。
 時代も思想も大きく隔たりのある D-112EXT と D-102A ですが、ラインアップの中では同じようなポジション。スタンダードより、ちょっとイイ、みたいな。
時代も思想も大きく隔たりのある D-112EXT と D-102A ですが、ラインアップの中では同じようなポジション。スタンダードより、ちょっとイイ、みたいな。
仕様を比べてみると…
D-102A: 50Hz~35kHz/Max 80W/6Ω/89dB/w184xh298xd237mm/5.2kg
D-112EXT: 60Hz~100kHz/Max 80W/6Ω/84dB/w162×h267×d271mm/4.8kg
再生周波数帯域がずいぶん上まで伸びてますね。ハイレゾ対応を唱うのも大変だ(笑)。使用頻度を考えると存在感が軽い方が望ましい私にしてみれば、ほんの少しでも小型化されている点が◎。
 現在使っているメインユニットは、ONKYO CR-N755。D-112EXT とは同世代で、しかもセット品としても販売されていたくらいなので、相性の心配はナシ。
現在使っているメインユニットは、ONKYO CR-N755。D-112EXT とは同世代で、しかもセット品としても販売されていたくらいなので、相性の心配はナシ。
で、その音は、といえば。過去に使っていた ONKYO のスピーカー(2セット)は、ややメリハリに欠けるけど中音域のツヤが嬉しいような印象を持っていたのですが、今回のは割と音圧の高いズンドコ系に寄ってるような気がします。小型ウーファーで足りない低音域をバスレフでゴッソリ稼いでいるのでしょう。今風の音、とも言えるんでしょうかね。とはいえ、米国ブランド品ほどドコドコしてはいないですし、リーズナブルな価格含め、全体的なバランスとしては良いんじゃないかと。なんて、破れたコーンに気づかなかった私の耳をしての感想ですけど(笑)。
しっかし、これで INTEC 205 関連モデルが手元から完全に消え失せました。 長きに渡りご苦労!であります。

 春先から夏場にかけて行っていた
春先から夏場にかけて行っていた  ブランド名はウムラウト混じりだけれど、商品サイトによると発売元は日本企業。雰囲気からして完全な商社って訳でもなくって開発も行っているっぽい。そして生産国は台湾。なんか産業のドーナッツ化が進みはじめた 90年代前半を彷彿とさせる組み合わせというか、近頃ありがちな「米国開発・中国生産」よりも世代的に親近感をもてる組み合わせというか(笑)。
ブランド名はウムラウト混じりだけれど、商品サイトによると発売元は日本企業。雰囲気からして完全な商社って訳でもなくって開発も行っているっぽい。そして生産国は台湾。なんか産業のドーナッツ化が進みはじめた 90年代前半を彷彿とさせる組み合わせというか、近頃ありがちな「米国開発・中国生産」よりも世代的に親近感をもてる組み合わせというか(笑)。 仕様面で私が DAC(&ヘッドフォン・アンプ)に求めていたのは、「標準プラグのヘッドホン端子」「ステレオ PIN プラグ出力」「48kHz 以上の音源対応」「Mac でドライバ要らず」だったので、当然、それら要件は満たしています。さらに、デジタル光角型入出力端子も付いてるぜ、と。
仕様面で私が DAC(&ヘッドフォン・アンプ)に求めていたのは、「標準プラグのヘッドホン端子」「ステレオ PIN プラグ出力」「48kHz 以上の音源対応」「Mac でドライバ要らず」だったので、当然、それら要件は満たしています。さらに、デジタル光角型入出力端子も付いてるぜ、と。 普段繋いでいるヘッドホンは、オーディオテクニカの ATH-PRO5MK3。いわゆるスタジオ向けモニター用(とメーカーが謳っている)密閉型です。数年前まで同シリーズの初期型を使っていて、値段の割には悪くなかったこともあって、外装がボロボロになって買い替えを考えた時に(余り)迷わず3代目へ世代交代していた次第。
普段繋いでいるヘッドホンは、オーディオテクニカの ATH-PRO5MK3。いわゆるスタジオ向けモニター用(とメーカーが謳っている)密閉型です。数年前まで同シリーズの初期型を使っていて、値段の割には悪くなかったこともあって、外装がボロボロになって買い替えを考えた時に(余り)迷わず3代目へ世代交代していた次第。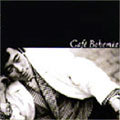 1980年デビューなんで、ずっと耳にしていることになりますね。ただ、82年頃に親からラジカセを買ってもらって以来、洋楽一辺倒になってしまったので、当時はあまり気に留めていませんでした。大学浪人中に知人から『Cafe Bohemia』を勧められた時に「日本人でもこんな音楽できる人いるんだー」なんて、お前は何様な感想を抱いてから『moto singles』購入を機にアルバムを追っかけ始めて現在に至ります。
1980年デビューなんで、ずっと耳にしていることになりますね。ただ、82年頃に親からラジカセを買ってもらって以来、洋楽一辺倒になってしまったので、当時はあまり気に留めていませんでした。大学浪人中に知人から『Cafe Bohemia』を勧められた時に「日本人でもこんな音楽できる人いるんだー」なんて、お前は何様な感想を抱いてから『moto singles』購入を機にアルバムを追っかけ始めて現在に至ります。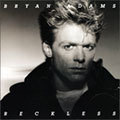 この人も80年デビューだ。初めて聞いたのは「Run to You」。この曲が入ったアルバム『Reckless』は大ヒットしましたねぇ。私的には次作『Into the Fire』の重い感じも好きなんですけど。当時からコンスタントにアルバムを買い続けてます。
この人も80年デビューだ。初めて聞いたのは「Run to You」。この曲が入ったアルバム『Reckless』は大ヒットしましたねぇ。私的には次作『Into the Fire』の重い感じも好きなんですけど。当時からコンスタントにアルバムを買い続けてます。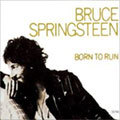 「Hungry Heart」で存在を知って、「Born to Run」でシビれてしまいました。で、初めて買ったロックのCDが『Born to Run』。90年代に入ってから余り聴かなくなって、『Magic』からまたアルバムを買うようになりました。最近だと『Wrecking Ball』が素敵。もはや、いいお歳ですけどね(笑)。
「Hungry Heart」で存在を知って、「Born to Run」でシビれてしまいました。で、初めて買ったロックのCDが『Born to Run』。90年代に入ってから余り聴かなくなって、『Magic』からまたアルバムを買うようになりました。最近だと『Wrecking Ball』が素敵。もはや、いいお歳ですけどね(笑)。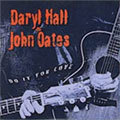 曲数はダリルのソロアルバム含み。「Kiss on My List」が慣れ初めだったかな。70-80’s の代表格ではありますが、私的にはポップス色が薄れて落ち着いた90年代以降のアルバムの方が好み。ダリルの歌うのが大好き!みたいな雰囲気が良いんですよねー(ロッド・スチュワートとかドリー・パートンあたりにも同じ気配を感じたり)。1995年の武道館ライブに行って、ダリルの生声がアルバムと全く変わらないのに驚きましたわい。
曲数はダリルのソロアルバム含み。「Kiss on My List」が慣れ初めだったかな。70-80’s の代表格ではありますが、私的にはポップス色が薄れて落ち着いた90年代以降のアルバムの方が好み。ダリルの歌うのが大好き!みたいな雰囲気が良いんですよねー(ロッド・スチュワートとかドリー・パートンあたりにも同じ気配を感じたり)。1995年の武道館ライブに行って、ダリルの生声がアルバムと全く変わらないのに驚きましたわい。 ELOの存在を知ったのは「Secret Message」でしたが、初めて耳にしたのはオリビア・ニュートン・ジョンの歌という認識で「Xanadu」でありました。初めて洋楽でハマったグループで、初めて買った洋楽LPが『Out of the Blue』、初めて買った洋楽CDが『ELO’s Greatest Hits』、図書館で初めて借りたLPが『Discovery』と初めてづくし。さらに掘り下げて、ジェフ・リン絡みのアルバムを追っかけるようになり(ジェフの音は聴いてソレと分かっちゃうから追いやすかったのね)、いい具合にアーティストの裾野を広げる機会をいただきました。
ELOの存在を知ったのは「Secret Message」でしたが、初めて耳にしたのはオリビア・ニュートン・ジョンの歌という認識で「Xanadu」でありました。初めて洋楽でハマったグループで、初めて買った洋楽LPが『Out of the Blue』、初めて買った洋楽CDが『ELO’s Greatest Hits』、図書館で初めて借りたLPが『Discovery』と初めてづくし。さらに掘り下げて、ジェフ・リン絡みのアルバムを追っかけるようになり(ジェフの音は聴いてソレと分かっちゃうから追いやすかったのね)、いい具合にアーティストの裾野を広げる機会をいただきました。 「Rosana」「Africa」あたりが慣れ初め。音の広がりとまとまり具合の心地よさ、それにいろんなジャンルの音楽を楽しめるグループとして継続して聴いてます。主要メンバーが抜けたり他界したりしていて、この先どうなるんだろうという感じではありますが…。私的にジョゼフ・ウィリアムスの声が好きなので「Sevence One」がお気に入り。最新作の『TOTO XIV』もイイ感じ。
「Rosana」「Africa」あたりが慣れ初め。音の広がりとまとまり具合の心地よさ、それにいろんなジャンルの音楽を楽しめるグループとして継続して聴いてます。主要メンバーが抜けたり他界したりしていて、この先どうなるんだろうという感じではありますが…。私的にジョゼフ・ウィリアムスの声が好きなので「Sevence One」がお気に入り。最新作の『TOTO XIV』もイイ感じ。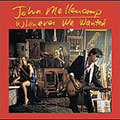 意に沿わぬ芸名を付けられて、段階的に本名に戻していった苦労人(なのか?)。「Jack and Dian」でシビれました。この人もコンスタントにアルバムを出し続けているので、目に留まった時に買ってます。
意に沿わぬ芸名を付けられて、段階的に本名に戻していった苦労人(なのか?)。「Jack and Dian」でシビれました。この人もコンスタントにアルバムを出し続けているので、目に留まった時に買ってます。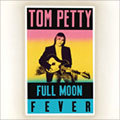 ELOのジェフ・リン繋がりで聴くようになった人(達)。ソロでもバンドでも覆面バンドでも絡んでたものね。『Full Moon Fever』は、TPらしさ、TP&THBらしさ、ジェフらしさがいい具合にバランスの取れた良作アルバムでありますね。
ELOのジェフ・リン繋がりで聴くようになった人(達)。ソロでもバンドでも覆面バンドでも絡んでたものね。『Full Moon Fever』は、TPらしさ、TP&THBらしさ、ジェフらしさがいい具合にバランスの取れた良作アルバムでありますね。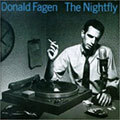 フェイゲンのアルバム『The Nightfly』をいたく気に入ってしまって、過去に遡ってスティーリー・ダンを聴き始め、その後出たアルバムはどっちも買うようになりました。そういや、ベッカーのソロは聴いてなかったな…。
フェイゲンのアルバム『The Nightfly』をいたく気に入ってしまって、過去に遡ってスティーリー・ダンを聴き始め、その後出たアルバムはどっちも買うようになりました。そういや、ベッカーのソロは聴いてなかったな…。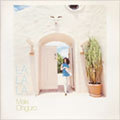 ようやく二人目の日本人。「男で聴くのって珍しいよねー」と言われたことがありますが、そんなものなのかなー。90年代の邦楽(いわゆるJ-POP)はドライブミュージック比重が大きかったのですが、大黒摩季は部屋でも聴く気になれたから枚数が増えた、て感じでしょうか。『O』で買うのを止めちゃいましたけど。
ようやく二人目の日本人。「男で聴くのって珍しいよねー」と言われたことがありますが、そんなものなのかなー。90年代の邦楽(いわゆるJ-POP)はドライブミュージック比重が大きかったのですが、大黒摩季は部屋でも聴く気になれたから枚数が増えた、て感じでしょうか。『O』で買うのを止めちゃいましたけど。 自分でも意外なくらい多くって、サザンよりちょい下で、ユーミンや渡辺美里と同数でした。この人は、完全にドライブ・ミュージック。大学時代に地元の仲間内で『非実力派宣言』が妙に流行って、「今度、どこか連れてってくださいよー」「はーい」みたいに合いの手を入れながら夜中に何処へともなく車を走らせてたんですね。さすがに今、聴くのはちょっと照れますわね(笑)。
自分でも意外なくらい多くって、サザンよりちょい下で、ユーミンや渡辺美里と同数でした。この人は、完全にドライブ・ミュージック。大学時代に地元の仲間内で『非実力派宣言』が妙に流行って、「今度、どこか連れてってくださいよー」「はーい」みたいに合いの手を入れながら夜中に何処へともなく車を走らせてたんですね。さすがに今、聴くのはちょっと照れますわね(笑)。